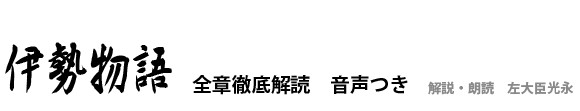六十 花橘
むかし、男ありけり。宮仕へいそがしく、心もまめならざりけるほどの家刀自(いえとうじ)、まめに思はむといふ人につきて、人の国へいにけり。この男、宇佐の使にていきけるに、ある国の祇承(しぞう)の官人の妻(め)にてなむあると聞きて、「女あるじにかはらけとらせよ。さらずは飲まじ」といひければ、かはらけとりていだしたりけるに、さかななりける橘をとりて、
さつき待つ花たちばなの香をかげばむかしの人の袖の香ぞする
といひけるにぞ思ひいでて、尼になりて山に入りてぞありける。
現代語訳
昔、男がいた。宮仕えに忙しく、誠実に愛情を妻に注いでやることができず、妻は愛情を注いでくれる男についていって、その男の任地へ行ってしまった。
この男が宇佐の勅使として九州へ下った際、かつてのわが妻がある国の接待役の役人の妻になっていると聞いて、「この家の主婦に盃を取らせよ」と言ったので、主婦が盃を取り出したところ、男はつまみの橘を取って、
五月を待って咲く橘の花の香りをかぐと、昔なじみの人の袖の香りがします。
と歌を詠んだことに女は、軽率にも家を飛び出したことを後悔して、尼になって山に篭って暮らしたのだ。
語句
■まめ 誠実に愛情を注ぐこと。 ■家刀自 妻。■宇佐の使 朝廷から九州大分の宇佐神宮に派遣される使い。 ■祇承の官人 宇佐の使を立てるとき、その接待をする役人。■女あるじ 主婦。 ■かはらけ 素焼きの盃。
解説
仕事が忙しく、なかなか妻にかまってやれませんでした。
そんな妻に言い寄ってくる男がありました。なあ、俺はあんたのことが好きなんだ。
あんな、何もしてくれない夫なんてうっちゃって、俺といっしょになろうぜ。
ああ、そんな、でも…結局、妻は男の誘いに乗り、夫のもとを去ります。
さてこの夫が、大分の宇佐八幡宮へ奉納の勅使として
赴いた時、途中の国で、
かつての自分の妻が、勅使接待役の役人の妻になっていると聞いて、
呼び出します。
もとの妻が、御簾の向うからお酒をトットットと注ぐと、
男は、お膳の上に酒の肴として載せてあった橘の実を手に取って、
五月待つ花橘の香をかげば
昔の人の袖の香ぞする
五月待つこの季節。花橘の香をかげば、
昔の人の袖の香りがするなあ。
その歌をきいて、女は、
「ああ…あの人だわ」
いたたまれなくなって、尼になって
山寺にこもり、余生をすごしたということです。